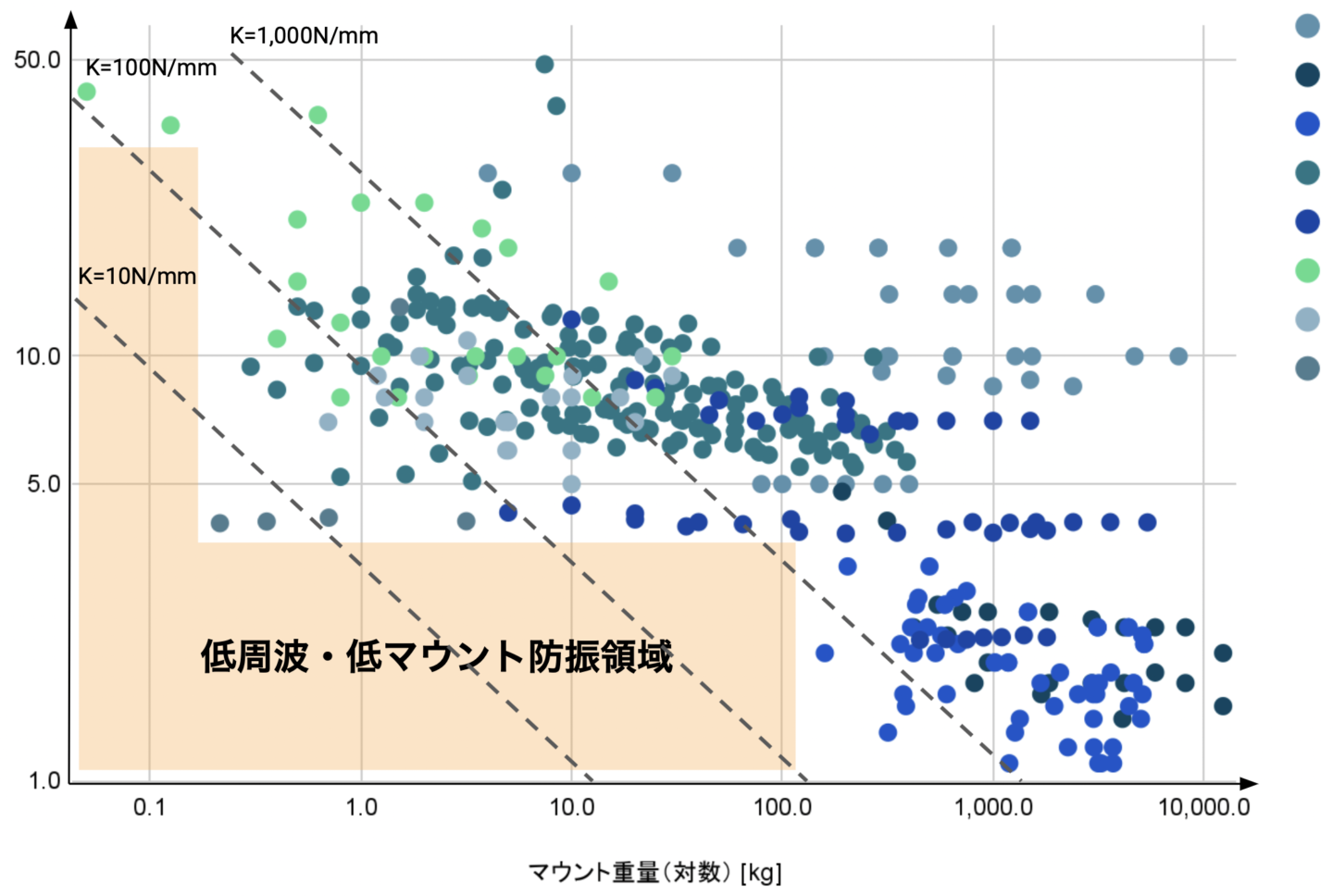1質点系の動的な性能について
以下のような質量 m、バネ剛性 k の非減衰の1質点のバネマス系について考えます。
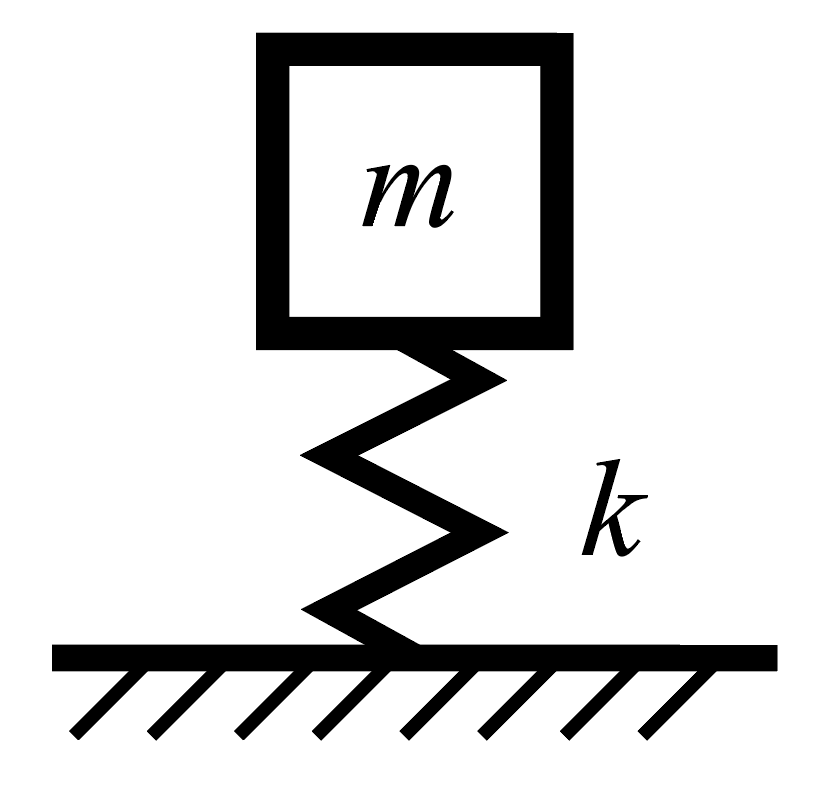
自由振動
質点が自由振動している状態での変位および力の関係は以下のように表すことができます。
\begin{align}
m \ddot{x} + kx = 0 \tag{1-1} \\
\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0 \tag{1-2} \\
\omega_n^2 = \frac{k}{m} \tag{1-3}
\end{align}上記微分方程式の一般解は以下のようになり、オイラーの公式よりサイン波で表される単振動になります。
x=Ae^{i\omega_n t + \delta}Aは最大振幅、\delta は位相差で初期値に依存する値です。一般解からわかるように \omega_n は 2\pi 秒内で何回振動するかを表す量で固有円振動数と呼ばれます。
固有円振動数 \omega_n は、固有周期 T、固有周波数 f_n とは次の関係があります。
f_n = \frac{1}{T} = \frac{\omega_n}{2 \pi} = \frac{1}{2 \pi} \sqrt{\frac{k}{m}}
\tag{1-4}式(1-4)より質量が一定の場合は、剛性の平方根に比例して固有周波数は高くなること、つまり剛性が高くなる(固くなるほど)固有周波数が高くなることがわかります。
強制振動
次に以下のような強制振動の問題において固有周波数が変化すると応答がどのように変化するかを考えます。
式(1-1) で扱っていた自由振動の問題に対して、円振動数 \omega、振幅 |F_0| の強制振動 F_0 = |F_0| e^{i \omega t} が与えられた状況を考えます
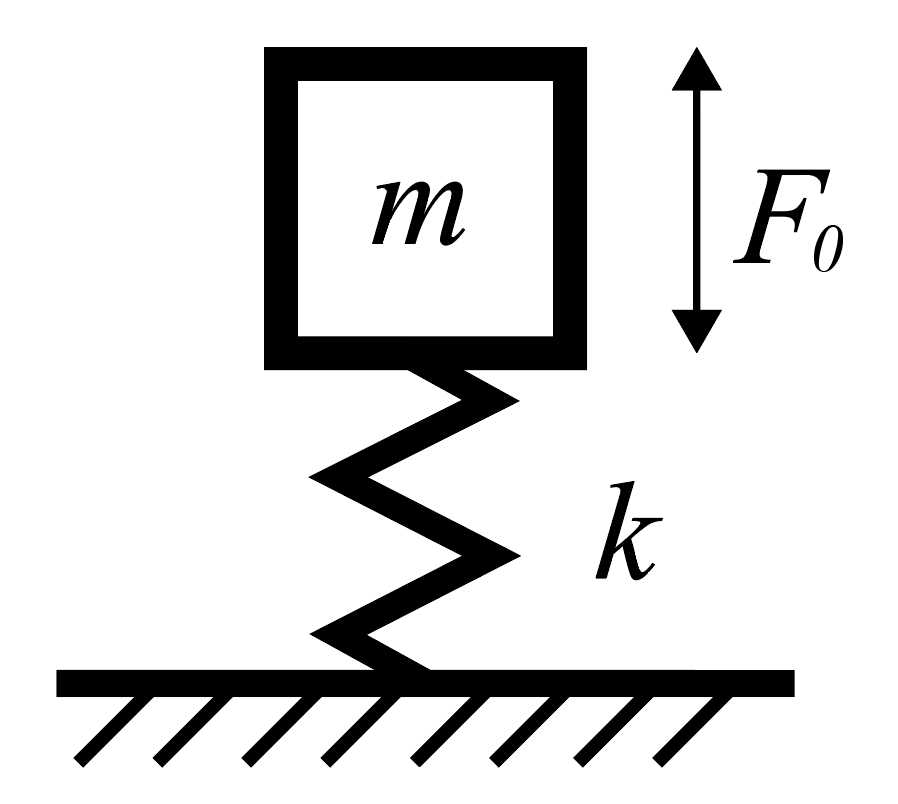
質点周りの力の釣り合いより、加振された質点の運動方程式は以下のようになります。
\ddot{x} + \omega_n^2 x = F_0
\tag{1-5}一方で、このバネを介して振動が伝わり、支持点側で発生する反力 F は、バネが変形することによって発生するため式(1-5)の2項目から、支持点まわりの力の釣り合いを考えると次のようになります。
\omega_n^2 x = F
\tag{1-6}以上より振動源から支持部への振動の伝達率 T_r は 式(1-5)、式(1-6) の比をとって以下のようになります。
\begin{align}
T_r &= \left|\frac{F}{F_0} \right|
= \left|\frac{\omega_n^2 x}{\ddot{x} + \omega_n^2 x} \right|
= \left|\frac{1}{1 + \frac{1}{\omega_n^2} \frac{\ddot{x}}{x}} \right| \\
&= \left|\frac{1}{1 + \frac{-\omega^2}{\omega_n^2}} \right|
= \left|\frac{1}{1 - u^2} \right|
\tag{1-7}
\end{align}u は加振周波数と1質点系の固有周波数の比(u=\frac{\omega}{\omega_n} = \frac{f}{f_n})、x は式(1-5) の形式の微分方程式の一般解 x = A e^{i \omega t} を使用して解いています。
式(1-7) をグラフ化すると以下になります。
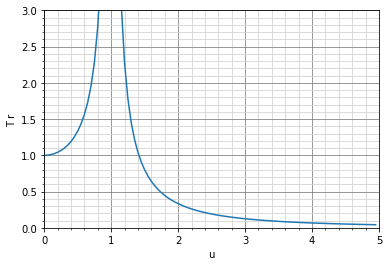
これらより次のことがわかります。
u = 1のとき、振動が大きく増幅して伝達される(共振現象)uが\sqrt{2}以下の範囲では常に振動が増幅されるuが\sqrt{2}を超えたときはじめて振動伝達率Trの値が 1 を下回り防振効果を発揮する
つまり防振したい場合は、周波数の比を \sqrt{2} 以上にする必要があります。
具体的な防振設計例
100Hz で加振される 1kg の装置から発生する振動の伝達を \frac{1}{8} となるように防振したい場合、周波数比 u=3 となり目標の固有周波数は式(1-7) より以下になります。
3 = \frac{100}{f_n}, \quad
\tag{1-8}
f_n \fallingdotseq 33 [\rm{Hz}]式(1-4) よりこのときのバネ剛性 k は次のようになります。
\frac{100}{3} = \frac{1}{2 \pi} \sqrt{\frac{k}{1}}, \quad
k = \left( \frac{200}{3} \pi \right)^2 \fallingdotseq 43900 [\textrm{N/m}] = 43.9 [\textrm{N/mm}]
\tag{1-9}実際の防振設計では、既製品で上記で求まった性能とぴったり一致する部材があることは少ないので近い値の部材をカタログから探すなどします。
各防振部材メーカーはウェブやカタログなどに選定フローがあり細かく計算しなくともどういった防振部材を選べばいいか書いてあったり表やグラフで求められる場合が多いです。
質量と周波数の関係
複数の質量と加振周波数の組み合わせでの防振について計算した結果を以下の表にまとめました。
質量 m [kg] |
加振周波数 F_0 [Hz] |
伝達率が 1/8 となる(u = 3) となる固有周波数 F_n [Hz] |
バネ剛性 k [N/mm] |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 33 | 43.9 |
| 0.1 | 100 | 33 | 4.39 |
| 0.01 | 100 | 33 | 0.439 |
| 1 | 10 | 3.3 | 0.439 |
| 0.1 | 10 | 3.3 | 0.0439 |
| 0.01 | 10 | 3.3 | 0.00439 |
| 1 | 1 | 0.33 | 0.00439 |
| 0.1 | 1 | 0.33 | 0.000439 |
| 0.01 | 1 | 0.33 | 0.0000439 |
このように、軽いものをより低い加振周波数でも防振するためには、より低い剛性のバネが求められることがわかります。
このバネ剛性で具体的にはどのような形状の部材があるかは、例えばモノタロウさんやミスミさんなどで、バネ剛性の値から部品を検索することができるので、興味がある方は調べてみてください。
上記表にある 1kg の質点を 10Hz で加振したときに防振するために必要な剛性 0.439N/mm の部材の一例として単純なコイルばねの以下のような既製品の部材がありました。
| 材質 | 自由高(mm) | 外径(Φmm) | 線径(Φmm) | ばね定数 (N/mm) |
|---|---|---|---|---|
| SUS304 | 40 | 11 | 0.8 | 0.44 |
1質点系の静的な性能について
これまで計算してきた振動に対する問題(動的な問題)に対して、以下のように重力加速度 g がかかるのみの部材の静的な状態について考えます。
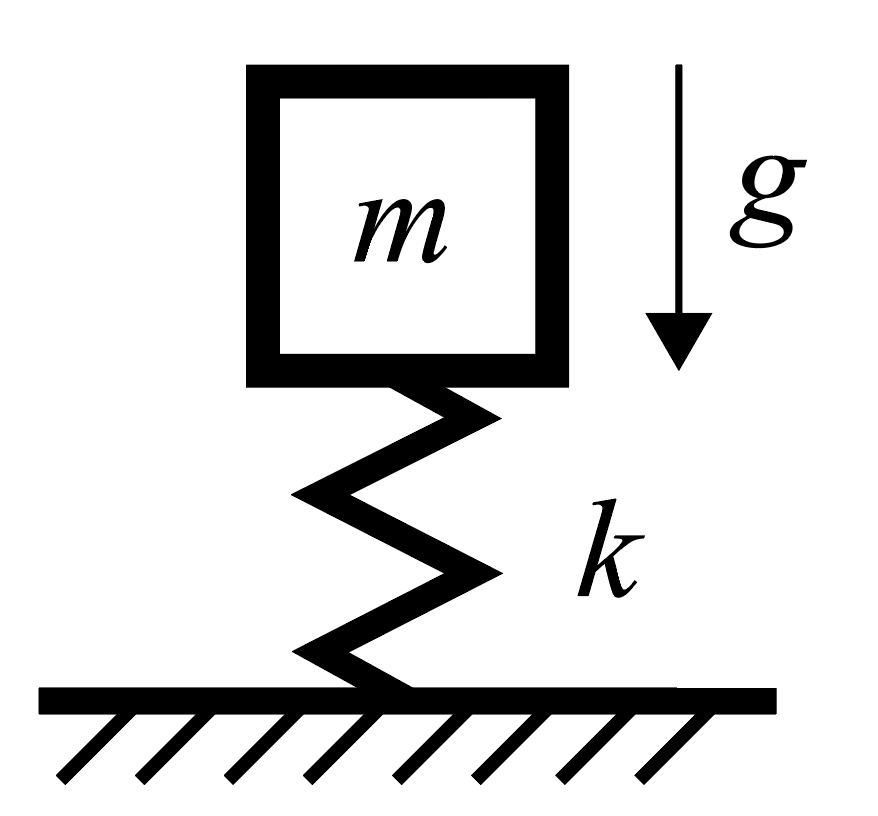
自重でのたわみ \delta は力のつり合いより下式になります。
\delta = \frac{m g}{k}
\tag{2-1}式(2-1)より、質量が一定の場合は剛性が大きくなるほどたわみが小さくなることがわかります。
1kg のものを 10Hz の加振に対して防振に必要だと求めた上記表のコイルばねの静的な変位を考えます。
\delta = \frac{1 \times 9.8}{0.44} = 22.2 \textrm{mm}
\tag{2-2}静的たわみ量が 22.2mm となり、バネの自然長 40mm の半分以上を静的な荷重で変形してしまっています。
防振用途での使用する際はこの変位から強制振動時の変形が加わるので、このように静的な状態で大きく変形してしまっている場合は、強制振動時の変形で底付きが発生し(バネが40mm変形してバネが接触し)防振効果を失い、衝突による大きな荷重が防振対象に掛かる可能性があります。
上記例では 1kg、10Hz の防振ですが、より低い周波数の防振の場合を想定し 1kg、1Hz の防振を考えるとバネ剛性 k は1/100 になります。このときの変形量は 22.2 \times 100 = 2220\textrm{[mm]} = 2.22\textrm{[m]} と非現実的な値となり、これまで紹介してきた手法では防振が困難な結果です。
剛性-質量-周波数のトレードオフについて
これまで示してきた動的な特性と静的な特性をまとめると、以下のトレードオフがあることがわかります。
- 剛性が小
- 1次固有周波数が低くなるため、より低周波数から防振することができる
- 静的たわみが大きくなり、防振対象物を設置しただけで過大な変形が発生し底付きする可能性がある。
- 剛性が大
- 1次固有周波数が高い周波数になるため、防振が難しくなる
- 静的たわみが小さくなり、重量物でも安定して支えることができる。
弊社で以前に既製品の防振部材を調査した結果が以下です。
低い周波数での防振を行おうとすると静的な変位が過大になってしまうこのトレードオフがあるため、低周波数の範囲で既製品の防振部材が市販されていないことがわかります。
低周波数の防振を実現しているグラフの右下の点の部材は、空気バネ方式と呼ばれる特殊なバネ剛性を持つ部材で防振を行っています。
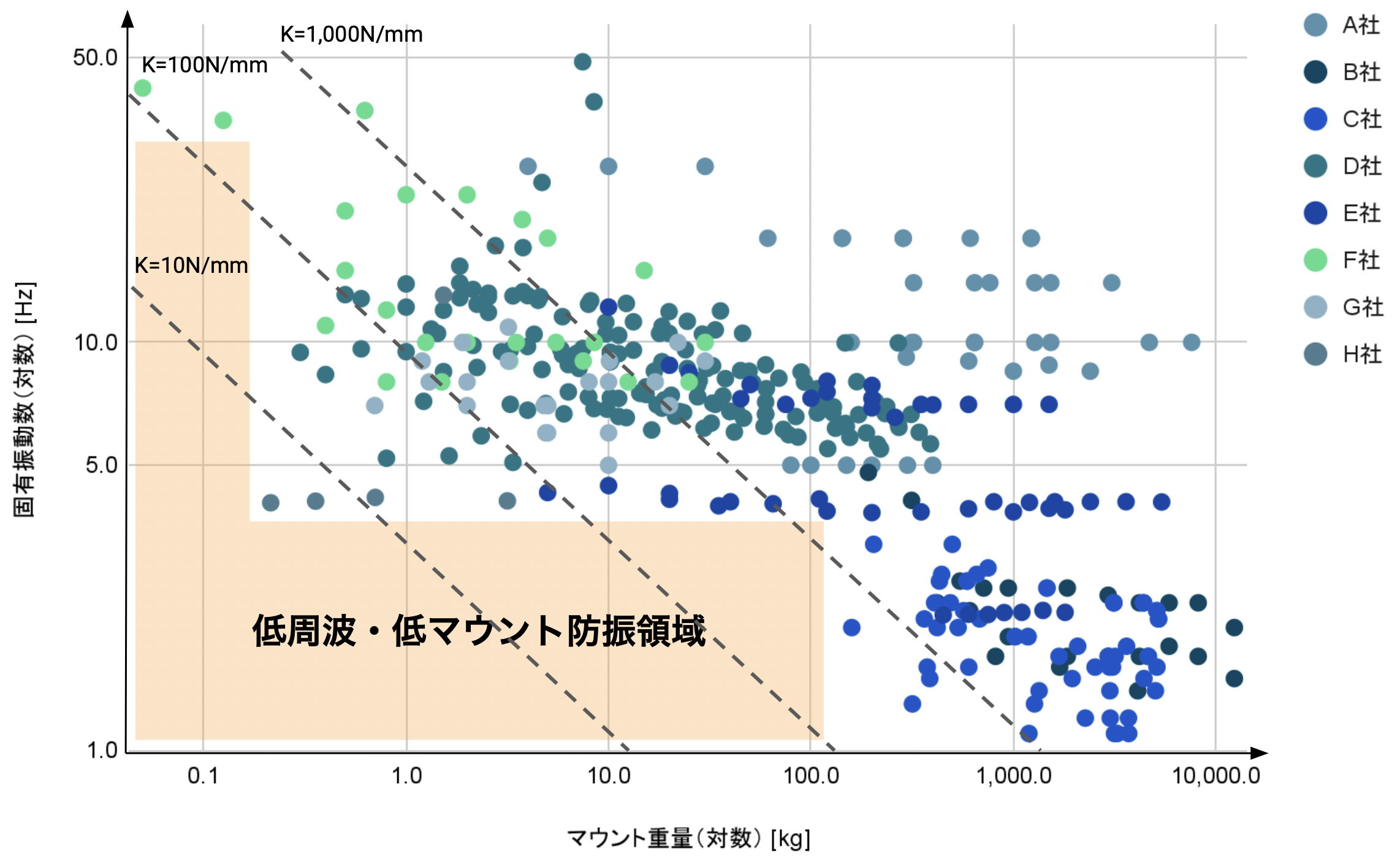
まとめ
一般的な動剛性と静剛性、及びそれらから求まる防振のトレードオフについて紹介しました。
次の記事では、最後に紹介したトレードオフを突破できる可能性のある構造メタマテリアルの一つの QZS と呼ばれる構造の具体的な内容について紹介します。